皆さんこんにちは。今回は「避難訓練等が義務になっている施設について」解説していきます。
以前の記事で少し触れましたが、
避難訓練(以下、消防訓練等と言います)が義務になっている施設が存在しています。
していなければ法令違反となってしまい、知らなかったでは済まされません。
今回でしっかり勉強していきましょう。
1 結論
最初に答えを説明すると、
「令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物」
+
「防火管理者を定めなければならない防火対象物」
↓
「消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施」
これが結論です。
以下より詳しく説明します。
2 義務になっている法律は?
「消防法」という法律で定められています。
具体的には、消防法施行規則第3条第10項で定められており、条文を読むと、
「令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第3条の2第2項の消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。」
とあります。
訳わかりませんよね。
安心してください。解説していきます。
3 まず、法律について
法律にはざっくり分けると3つのレベルがあります。
これが、「消防法」「消防法施行令」「消防法施行規則」です。
それぞれの具体的なイメージを消火器になぞらえて説明すると、
- 消防法(基本的なルール):「建物には火災が起きたときに使うための消火器を置きましょう。」と書かれてます。
- 消防法施行令(具体的なルール):「消火器は、一定の広さ以上の建物に必要です。どこに設置するかは、建物の広さや用途によって決めます。」と書かれています。
- 消防法施行規則(もっと詳しい運用方法):「消火器は、この場所(ドアの近くや人がすぐに見つけられる場所)に設置し、点検記録を必ず残してください。」と書かれています。
といった具合です。イメージ、掴めましたか?
4 令別表第1とは?
これは先ほど説明した「消防法施行令」の別にある表のことです。
具体的にはこれ↓
(参考)消防法施行令別表第1(令和6年4月1日 施行分を記載)
これの中の、「~(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物~」には消防訓練等が必要そうなことが分かりますね。
ちなみに防火対象物とは、主に建築物を指し、その中で火災予防に必要な建築物を取り上げたのが、上記の別表である。と考えて頂いて概ね合っています。
5 防火管理者とは?
法律的には、消防法第8条に記載されております。
その中で重要なのは、
「防火対象物の所有者等が、その規模に応じて、防火管理者を選任し、届出なければならない」
ということです。
↓その規模というのはこちらです。
(参考)防火管理者を定めなければならない防火対象物等(令和6年4月1日 施行分を記載)
ということは、
消防訓練等が義務であり、防火管理者が必要な防火対象物とは
「(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物で収容人員30人以上」
「ただし、(6)項ロは収容人員10人以上」
「また、(16)項イで(6)項ロが入っている対象物も収容人員10人以上」
となります。
6 それ以外の施設は避難訓練等をしなくて良いの?
以上が消防訓練等が必須である条件である防火対象物です。
それ以外の防火対象物では法律上、決まっていません。
しかし、学校ではしていたと思います。
防災意識が高い防火対象物の防火管理者の方々は独自に消防訓練等を実施しているのが実態です。
皆さんの子供頃は、先生方にしっかり守られていた訳ですね。
7 届出・お知らせ先は?
お近くの消防署へ訓練を実施する前に相談を行なってください。
また、記録をとっておき、消防署の立入検査の際に提出できるようにしてください。
もちろん、消防署へ訓練の依頼を行なっても良いです。
ただし、ご自身で行うときは注意が必要です。
・自動火災警報器と警備会社や自動で消防署へ自動連絡機能がなされている場合
避難訓練等行う時に、自動火災警報器(非常ベルが鳴るあれです)を押してしまうと、警備会社や消防車が飛んで来ます。ちゃんと訓練を行う旨連絡を入れておきましょう。
・通報訓練をする場合
同じ理由で119番通報を実際に用いて訓練を行う場合も同様です。事前に消防署へ連絡を入れて、実際に通報する際にも、「訓練です」の文言を言いましょう。
・消火訓練をする場合
消火器を用いるのはおすすめしません、消火器の説明をした際にも記載しましたが、一般的な消火器の中には粉が入っています。訓練で使用すると、ピンク色の粉まみれになりますので、消防署から水の消火器を借りるか、消防署から訓練の出向を依頼しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
少しでも皆様の職場などで消防訓練等を行うときの参考になれば幸いです。
今回もありがとうございました。


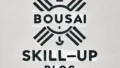

コメント