皆さんこんにちは。今回は危険物(第4類)について解説していきます。
もっとも身近な危険物はこの類の危険物かも知れませんね。
ということは需要が多いと思いますので、詳しく説明していけたらと思います。
一緒に勉強して行きましょう。
1 危険物の分類(消防法別表第一)の確認
以前、危険物は、消防法の規定により以下の6つの類別に分類されています。と
紹介しましたね。今回はこちらです。
「第4類(引火性液体):ガソリン、灯油、アルコール類など」
車の燃料に使ったり、暖房に使ったりする身近なものです。
2 第4類とは
そもそも第4類の定義とはなんでしょうか。
ざっくりお伝えすると「液体」であって、「引火性」を示すものです(消防法別表第一備考欄10)。
この2つが特徴です。
なので、「個体」とか「物質」とか書いてあったら、それは第4類ではないということですね。
3 引火性とは?
次に出てくる疑問は、「引火性」ですよね。
引火性とは、他の火元があって火がつくものです。
その火がつく温度を「引火点」と呼んだりします。
ちなみに「発火点」もあって、こちらは火元がなくても火がつく点のことを言います。
その引火点ごとに「第4類」の危険物の中でも、種類が分かれています。
| 名前 | 引火点等 | 主な種類 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点100℃以下又は 引火点ー20℃以下で 沸点(沸騰する点)が40℃以下のもの | ジエチルエーテル、二硫化炭素等 |
| 第1石油類 | 引火点21℃未満 | アセトン、ガソリン等 |
| アルコール類 | 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール | (消毒液ですとエタノール濃度が重量比で60%以上のものが危険物に該当すると言われています) |
| 第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満 | 灯油、軽油等 |
| 第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満 | 重油、クレオソート油等 |
| 第4石油類 | 引火点200℃以上250℃未満 | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 引火点250℃未満 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの |
以上が第4類の危険物です。
ちなみに引火点250℃以上の液体は「指定可燃物」の「可燃性液体類」といい条例で規制されます(危険物の規制に関する政令第1条の12)。
4 特徴・火災予防法
以下に特徴は次の5点です。
- 引火性の液体
- 蒸気の比重がすべて1より大きい(空間中では蒸気が下に溜まる)
- 液体の比重はほとんどが1より小さい(水に浮く)
- 水に溶けないものが多い(アルコールは溶ける)
- 電気を通さないものが多い(電気が蓄積されやすいため、放電しやすく火花が出やすい(冬の静電気をイメージして下さい))
火災予防法は次の7点です。
- 火種(炎や熱源)を近づけない。
- 容器をしっかり閉める。
- 換気の良い場所に置く。
- 温度が低く日の当たらない場所(冷暗所)に置く。
- (蒸気が発生しやすい取り扱いをする場合)低い位置に溜まった蒸気を屋外の高い場所に排出する。
- 静電気を発生させない(アース(接地)をとる。)。
- (著しく可燃性蒸気が発生する恐れのある場所)電気設備は防爆のものを使用する。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
第4類の危険物の特徴を大まかに解説させていただきました。
わかりやすい表現をしたつもりです。
こうして欲しい等の質問があればお気軽にお問合せください。
今回もありがとうございました。

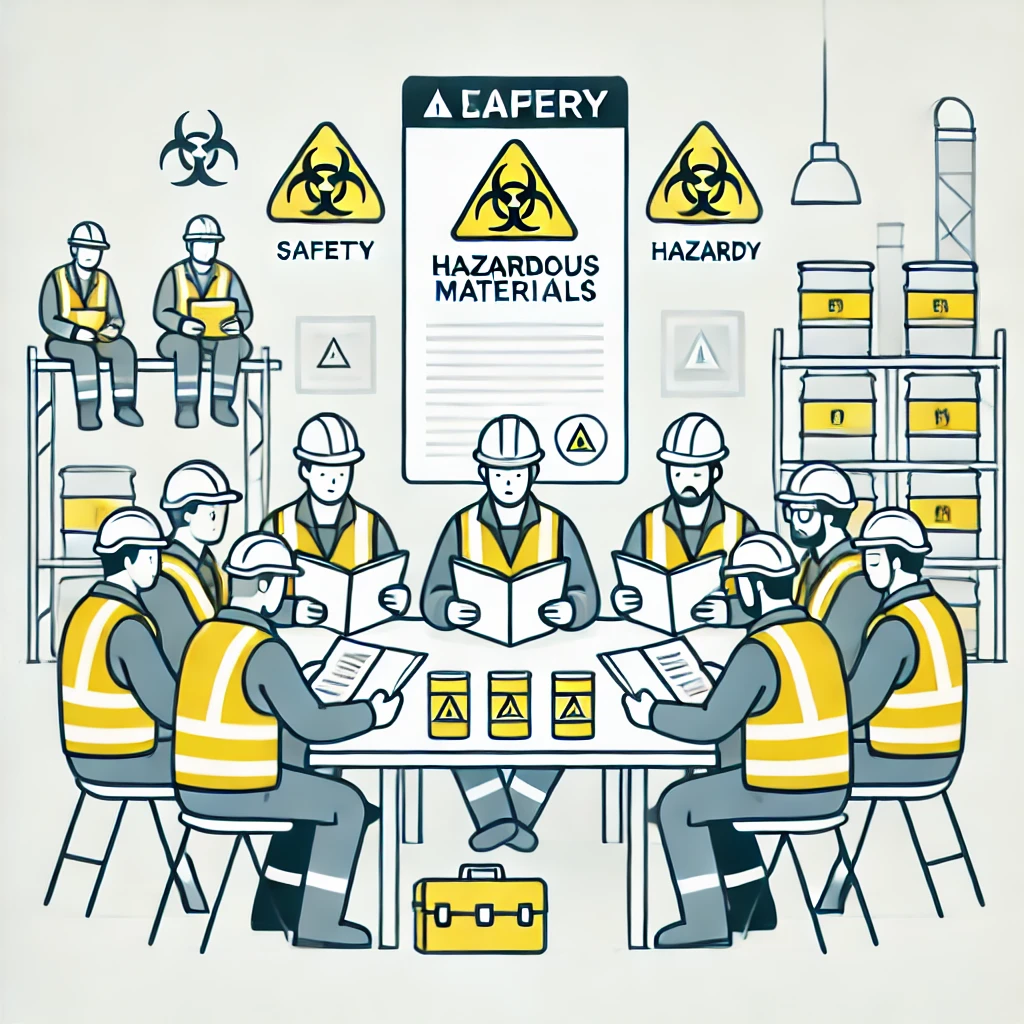


コメント