皆さんこんにちは。今回は危険物法令について解説していきます。
危険物は以前紹介した高圧ガスと同様に産業には欠かすことができない物品です。
しかしその取り扱いには危険が伴うため、法令に沿って規制されなければなりません。
その規制の方法を一緒に勉強していきましょう。
1 危険物とは?
「危険物」とは、消防法第2条第7項に記載されており、内容としては、火災の危険性が特に高い物質として指定されたものを指します。
これらの物質は、爆発しやすい、引火しやすい、酸化しやすいなどの性質を持つため、適切な管理が必要で、分類は以下の通りです。
危険物の分類(消防法別表第一)
危険物は、消防法の規定により以下の6つの類別に分類されています。
- 第1類(酸化性固体):硝酸カリウム、過マンガン酸カリウムなど
- 第2類(可燃性固体):赤リン、マグネシウム粉末など
- 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質):黄リン、カリウム、ナトリウムなど
- 第4類(引火性液体):ガソリン、灯油、アルコール類など
- 第5類(自己反応性物質):ニトロ化合物、有機過酸化物など
- 第6類(酸化性液体):過酸化水素、硝酸など
2 指定数量について
「指定数量」とは、消防法で定められた危険物ごとの貯蔵・取扱いの基準となる数量であり、消防法施行令別表第三に定められています。
この指定数量を超えて貯蔵・取扱いをする場合は、消防法に基づく許可や届出が必要となります。
また、この数量の5分の1以上の数量がある場合は、市町村の条例に従い、届出等が必要となります。
指定数量の例(第4類:引火性液体)
| 危険物 | 指定数量 |
|---|---|
| ガソリン | 200L |
| 灯油 | 1,000L |
| 軽油 | 1,000L |
| アルコール類 | 400L |
例えば、ガソリンを200L以上貯蔵する場合、市町村の消防機関に許可が必要となります。
3 指定数量の計算方法
異なる種類の危険物を併せて貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの指定数量の合計を超えていないかを確認する必要があります。この際、「指定数量の倍数」で計算を行います。
計算式
A/X + B/Y + C/Z ≤ 1
A, B, C = 各危険物の貯蔵・取扱量(Lまたはkg)
X, Y, Z = 各危険物の指定数量(Lまたはkg)
計算例
例として、ガソリン100L、灯油500L、軽油500Lを貯蔵する場合の計算は以下のようになります。
100/200 + 500/1000 + 500/1000
= 0.5 + 0.5 + 0.5
= 1.5
この場合、合計が1を超えているため、消防法上の許可が必要になります。
4 危険物の貯蔵・取り扱いについて
危険物を安全に管理するため、消防法では貯蔵方法や取り扱いの基準が定められており、詳細は危険物の規制に関する政令の第4章に記載されています。
以下は参考に危険物の規制に関する政令第25条第1項を記載しています。
- 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。
- 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
- 自然発火性物品(第3類の危険物のうち第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあつては水との接触を避けること。
- 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
- 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
- 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
ここではさわりだけなので、おいおい各類の性状等も説明していきますね。
まとめ
いかがでしたか。
危険物の規制に関して、触りだけでも理解できたかと思います。
他の記事では、もっと深く危険物の施設についても触れていければと思います。
今回もありがとうございました。

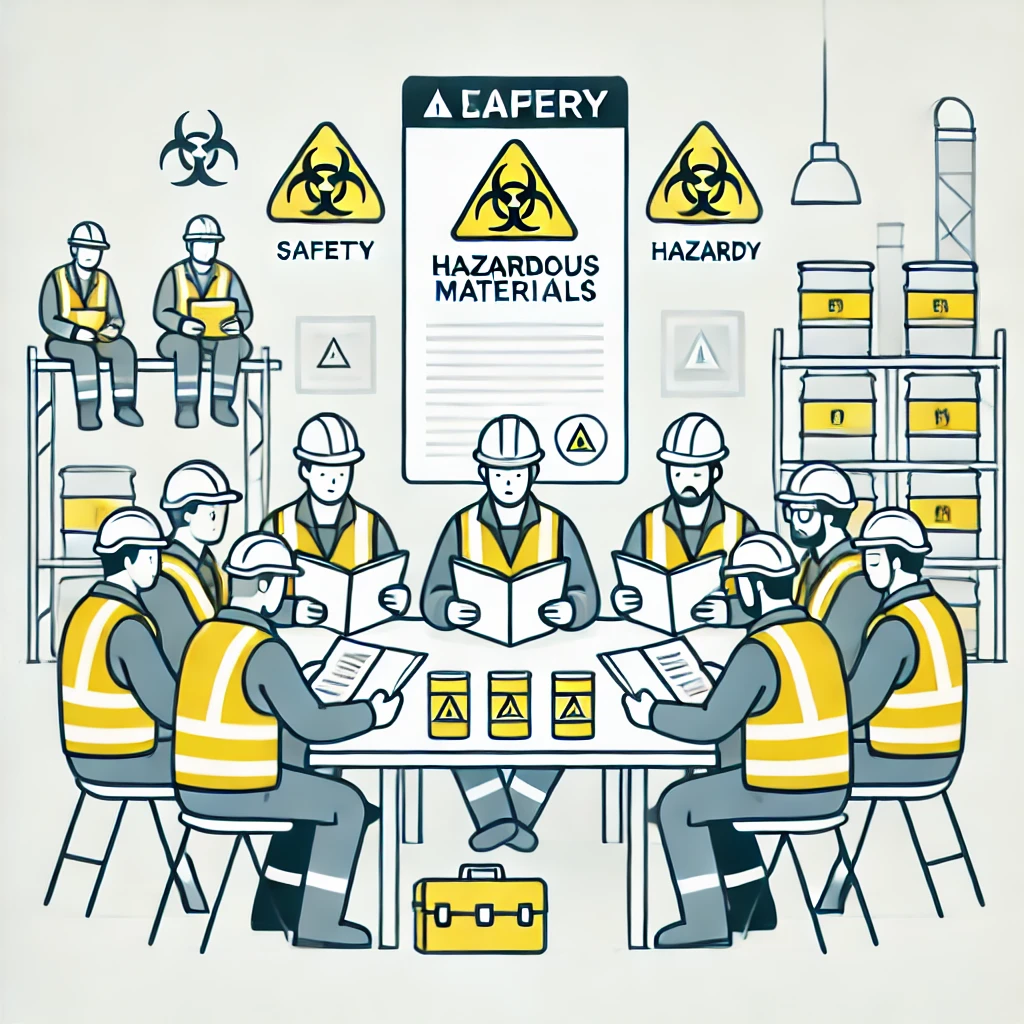


コメント