皆さんこんにちは。今回は消火器を設置する際の決まりについて解説していきます。
以前、消火器の使い方を解説しましたが、
「どこに・どれだけ・どのように」設置するかを疑問に思った方も多いと思います。
今回はその部分を一緒に学んでいきましょう。
なお、今回は少量危険物等は考えずに、防火対象物のみにスポットを当てて紹介していきます。
1 どこに
これは、消防法施行令第10条に定められており、以下のとおりです
一 次に掲げる防火対象物
- イ 別表第一(1)項イ、(2)項、(6)項イ⑴~⑶、(6)項ロ、(16の2)項~(17)項、(20)項に掲げる防火対象物
- ロ 別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡以上のもの
- イ 別表第一(1)項ロ、(4)項、(5)項、(6)項イ⑷、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項、(12)項~(14)項に掲げる防火対象物
- ロ 別表第一(3)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)
三 別表第一(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のもの
(参考)四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(法第2条第7項に規定する危険物(別表第二において「危険物」という。)のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で当該指定数量未満のものをいう。) 又は 指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を 貯蔵し、 又は 取り扱うもの
五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の
- 地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、
- 無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。) 、
- 3階以上の階で、
床面積が50㎡以上のもの
用語の定義はリンク先をご参照ください。
2 どれだけ
どのくらい消火器を置かなければならないか、それは消防法施行規則第6条に記載されています。
条文は検索していただいて、噛み砕いて記載します。
- まず、ここでは、建物全体の面積(延べ面積)をもとに、消火器の消火性能を数値化した「能力単位」を使って消火器の設置個数を求めます。
- よく見る消火器1本(10型)は3能力単位と数えます。これはA火災に対して、消火能力が3単位あるよという意味と思って下さい。
次に対象物の延べ面積ごとに、決まった定数で徐します。
- 令別表第一(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項及び(17)項に掲げる防火対象物=50㎡
- 令別表第一(1)項ロ、(3)項~(6)項、(9)項、(12)項~(14)項に掲げる防火対象物=100㎡
- 令別表第一(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項に掲げる防火対象物=200㎡
例)(15)項 1000㎡÷200㎡=5
=5能力単位以上の消火器が必要
=消火器が3能力単位としたら、2本必要
となります。
3 どのように
これは設置状況についてです。
まとめると、「消火器は、通行又は避難に邪魔でなく、使用する時に簡単に持ち出すことができる箇所に設置すること。具体的には、高さは床から1.5mの高さで、薬剤が変化等することなく、地震などで倒れることない場所に設置し、設置した箇所に、「消火器」と表示すること。」ということになります。
以下に根拠条文を記載します。
消防法施行令第10条第2項第2号
「消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。」
消防法施行規則第9条第1項第1~4号
一 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。
二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、~表示した標識を見やすい位置に設けること。
まとめ
いかがでしたか。
今回紹介した消火器の設置基準は一般的な事項をまとめました。
その他、他の消防用設備等を設置した場合、設置個数が減少したり、
市町村の条例で設置個数が増えたりします。
詳細はお近くの消防署へお尋ねください。
本日もありがとうございました。


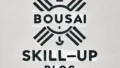

コメント