皆さんこんにちは。今回は高圧ガスについて解説していきます。
高圧ガスは、今や工業に欠かせないものになっていますが、とても高い圧力をかけていますので、同時に危険なものになっています。
一緒に学んで、安全に使用できるようにしていきましょう。
1 高圧ガスの定義
まず高圧ガスの定義を確認しましょう。
これは高圧ガス保安法第2条に定められており、主に「圧縮ガス」・「圧縮アセチレンガス」・「液化ガス」・「液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガス」に分けれます。
- 「圧縮ガス」
- 常用の温度において圧力が1メガパスカル(MPa)以上となる圧縮ガスであって、現にその圧力が1MPa以上であるもの
- 温度35度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス
- 「圧縮アセチレンガス」
- 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
- 温度15度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
- 「液化ガス」
- 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
- 圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
- 「液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガス」
- 前に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
ここでいう『常用の温度』とは、
- 圧縮水素運送自動車用容器にあっては65℃
- その他の容器にあっては40℃
とされています。
ざっくりここでは圧縮ガス1Mpa、液化ガス0.2Mpaを越えるか否かが鍵になると覚えておいて下さい。
2 高圧ガスの適用除外
適用除外されるガスの内容は9種類あり高圧ガス保安法第3条に記載されています。
なお、当該条の2項で書かれている内容は、分かりづらいと思いますので以下に内容を簡単に記載しています。
- 内容積1(デシリットル)dl以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、
- 「容器及び容器の付属品等」「帳簿の記載と保存等」「報告徴収、立入検査、事故届の規定」は適用しない。
ということになっています。
3 高圧ガスの製造・貯蔵・消費
高圧ガスを使う目的は主にこの3つが目的です。簡単に紹介します。
製造:ガスを作り出す行為のことを考えがちですが、これは違います。主に以下の場合が製造にあたります。
- 気体のガスの圧力を変化させる行為:例えばガスの圧力を①0Mpa→1MPa・②1Mpa→5Mpa・③5Mpa→1Mpa のように変化させる行為です。
- 液体のガスの圧力を変化させる行為
- ガスの状態を変化させる行為:例えば①気体のガスを、液体の高圧ガスにすること。②気化器で気化させることにより、液化ガス(高圧であることを問わない)を気体の高圧ガスにすること。 などを言います。
- 高圧ガスを容器に充填する行為:俗にいう移充填です。
貯蔵:社会一般的にいう貯蔵とは違い、広い意味になります。全て高圧ガスをという枕詞がつきます。
- 容器に充填したものの場合:配管に接続しないで容器として置いておくことです。また、充填配管で充填されそのままのものや消費用配管に接続し、消費し終わったままのものも貯蔵となります。 この際、輸送中は適用しません。しかし、車両に固定又は積載され、かつ、2時間以上一定場所にいる場合は含みます(消防車等は除く)。また、この場合、貯蔵所の許可・届出をした場所以外にこのような状態で置いておくことは禁じられています。
- 貯槽に充填したものの場合
- 容器及び貯槽以外の器(装置類)に充填したものの場合:容器に準じます。
- 冷凍設備に内に充填したもの:冷凍能力が20トン/日以上(冷媒ガスがCO2、フルオロカーボン、アンモニアの場合は50トン/日)で製造の用に供してない場合が適用されます。
消費:高圧ガスを廃棄以外の目的で減圧することと、それを使用するものを指します。
- 高圧ガスを減圧し、同種のガスにすること。
- 高圧ガスを異種の物質(高圧ガスを含む)にすることをいい、主に反応・燃焼・溶解等があげられます(液化ガスの気化は異種ではないとされています。)
まとめ
いかがでしたか。
高圧ガスについて軽く触れてみました。
特に、一般的な概念とは一線を画し、独自のルールとなる場合が多くあったかと思います。
今後は高圧ガス等についても色々解説していきたいと思います。
私も勉強のつもりで記載していますので、一緒に勉強できたらと思います。
今回もありがとうございました。


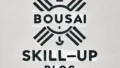

コメント